年賀状・暑中見舞い、はがき作成・印刷方法、年賀状ソフト等の情報を提供するサイトです。
年賀状・暑中見舞いドットコム

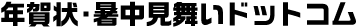
年賀状・暑中見舞い、はがき作成・印刷方法、年賀状ソフト等の情報を提供するサイトです。

季節の挨拶状
季節の挨拶状を年賀状ソフトで作成しよう! 作り方は「パソコン年賀状の作り方」をご参考に。
「筆まめ」なら、「年賀状文面~年賀状ソフト編1」の「文面デザイン読み込み」の要領で、使用するデザインやイラストを「年賀状」「喪中・欠礼」「暑中・寒中見舞い」など目的のカテゴリから選びます。基本的な操作は年賀状の作成と同じです。
年賀状
「年賀」とは、日頃お世話になっている人やご無沙汰している人に、新年を迎えるに際してあらたまって行う挨拶です。日頃のお付き合いに感謝し、今後の変わらぬ親交と一年の幸福を祈念します。
日本では古代から「年賀」の習慣がありましたが、明治になって郵便制度が整い郵便はがきが発行されると、はがきで年賀状を送る習慣が広まりました。
送る時期
近年、年賀状は元旦に届けるのが礼儀正しいとされていますが、本来は松の内(一般に1月7日まで)に届けば失礼にはあたりません。各地の郵便事情にもよりますが、年賀状を確実に元旦に届けるには、日本郵政グループの推薦投函日までに投函するようにしましょう。
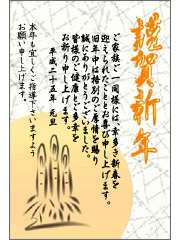
「年賀」とは、日頃お世話になっている人やご無沙汰している人に、新年を迎えるに際してあらたまって行う挨拶です。日頃のお付き合いに感謝し、今後の変わらぬ親交と一年の幸福を祈念します。
日本では古代から「年賀」の習慣がありましたが、明治になって郵便制度が整い郵便はがきが発行されると、はがきで年賀状を送る習慣が広まりました。
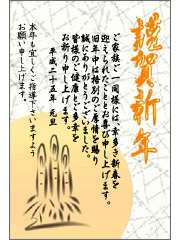
送る時期
近年、年賀状は元旦に届けるのが礼儀正しいとされていますが、本来は松の内(一般に1月7日まで)に届けば失礼にはあたりません。各地の郵便事情にもよりますが、年賀状を確実に元旦に届けるには、日本郵政グループの推薦投函日までに投函するようにしましょう。
書き方
年賀状特集から以下のページをご参考に!
>> 年賀状特集 > 年賀状の基本 > 年賀状の書き方・送り方
文例
年賀状や暑中見舞いなどの季節の挨拶状では、「拝啓」「敬具」などの頭語・結語は省略します。
喪中・年賀欠礼状(喪中はがき)
喪中欠礼状は、1年以内に近親者に不幸があったときに、年賀状の交換を辞退する旨を伝える書状です。
近親者のどの範囲まで喪中にするかは家により様々ですが、一般に自分を中心とした一親等(父母・配偶者・子)と、生計を共にしている二親等(祖父母・兄弟姉妹・孫)にあたる人が亡くなったときは喪中欠礼状を出す習慣があります。
送る時期
喪中欠礼状は、相手が年賀状を書く前に届けるようにします。年賀状を用意する前の11月中頃から12月初め、遅くても年賀特別郵便取扱が始まる前に届けましょう。

喪中欠礼状は、1年以内に近親者に不幸があったときに、年賀状の交換を辞退する旨を伝える書状です。
近親者のどの範囲まで喪中にするかは家により様々ですが、一般に自分を中心とした一親等(父母・配偶者・子)と、生計を共にしている二親等(祖父母・兄弟姉妹・孫)にあたる人が亡くなったときは喪中欠礼状を出す習慣があります。

送る時期
喪中欠礼状は、相手が年賀状を書く前に届けるようにします。年賀状を用意する前の11月中頃から12月初め、遅くても年賀特別郵便取扱が始まる前に届けましょう。
書き方
年賀状特集から以下のページをご参考に!
>> 年賀状特集 > 喪中はがき > 喪中・年賀欠礼状(喪中はがき)の書き方・送り方
文例
寒中見舞い
寒中見舞いは、厳寒期に相手の健康を気遣う便りです。
寒の入りから節分(立春の前日)までの、二十四節気の「小寒」と「大寒」に相当する期間が「寒中(寒の内)」で、この期間に寒中見舞いを届けます。
次のような場合も、寒中見舞いを送りましょう。
>> 年賀状特集 > 年賀状の基本 > 年賀状のマナー「出していない人から年賀状が届いたら」
>> 年賀状特集 > 年賀状の基本 > 年賀状のマナー「喪中に年賀状をいただいたら」
>> 年賀状特集 > 年賀状の基本 > 年賀状のマナー「喪中と知らずに年賀状を出してしまったら」
送る時期
寒中見舞いは、松が明けてから(松の内は一般に1月7日まで)、立春の前までに届けます。
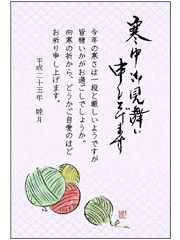
寒中見舞いは、厳寒期に相手の健康を気遣う便りです。
寒の入りから節分(立春の前日)までの、二十四節気の「小寒」と「大寒」に相当する期間が「寒中(寒の内)」で、この期間に寒中見舞いを届けます。
次のような場合も、寒中見舞いを送りましょう。
>> 年賀状特集 > 年賀状の基本 > 年賀状のマナー「出していない人から年賀状が届いたら」
>> 年賀状特集 > 年賀状の基本 > 年賀状のマナー「喪中に年賀状をいただいたら」
>> 年賀状特集 > 年賀状の基本 > 年賀状のマナー「喪中と知らずに年賀状を出してしまったら」
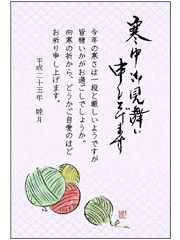
送る時期
寒中見舞いは、松が明けてから(松の内は一般に1月7日まで)、立春の前までに届けます。
書き方
文例集の以下のページをご参考に!
>> 文例集 > 季節の挨拶状と文例 > 寒中見舞い・余寒見舞いの書き方・送り方
文例
余寒見舞い
節分を過ぎ、寒が明ける「立春」からは、暦の上では春になります。春になっても残る寒さを「余寒」といい、立春以降は「寒中見舞い」ではなく「余寒見舞い」として送ります。
文例
暑中見舞い
暑中見舞いは、猛暑期に相手の健康を気遣う便りです。
二十四節気の「小暑」「大暑」に相当する期間が「暑中」で、この期間に暑中見舞いを届けます。暑中は「土用(立秋の前の18または19日間)」の期間にもあたるため、「土用見舞い」ともいわれます。
送る時期
暑中見舞いは、梅雨明け後、暑中の期間(立秋の前まで)に届けます。
書き方
暑中見舞い特集から、以下のページをご参考に!
>> 暑中見舞い特集 > 暑中見舞いの基本 > 暑中見舞い・残暑見舞いの書き方・送り方
>> 暑中見舞い特集 > 暑中見舞いの基本 > 暑中見舞い・残暑見舞いのマナー
文例
残暑見舞い
「立秋」からは、暦の上では秋になります。秋になっても残る暑さを「残暑」といい、立秋以降は「暑中見舞い」ではなく「残暑見舞い」として送ります。
送る時期
残暑見舞いは、立秋の後、処暑の候(8月23日~9月7日頃)までを目安に届けます。
書き方
暑中見舞いと同様ですが、日付などは「盛夏」ではなく、「晩夏」「立秋」「葉月」などを使いましょう。
